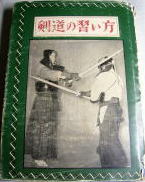| 2005年5月28日(土) | |||
| no.30 剣道の習い方 高野弘正 著 | |||
|
|||
今日の1冊は秘蔵の一冊である。私は10年ほど剣道を嗜んできた。その際のバイブルがこの本である。高野佐三郎。埼玉では有名な、ひょっとすると全国的に有名な剣道家である。その彼の息子が書いた本である。(佐三郎氏の著作では「剣道」というものがある。)内容は剣道の動作の初歩から実践までを網羅した剣道の参考書のようなものである。 では、なぜこの本が私にとってのバイブルとなりえたか、である。それは何故、この入手困難な本をここでオススメするか、という事でもある。理由は2つある。 まず第一にこの本の出た時期である。昭和28年。この時期は正に戦後一時期占領政策により途絶えた形となった剣道が再出発を迎えた時期である。その時期に出され本である為、戦後剣道初期のより原理的な思想が色濃く反映されている。つまり考えようによっては今の剣道の基本・根本が見て取れるのである。 もう一つはこの本のスタンスである。この本の題は「剣道の習い方」である。最初手に取った時はしっくりこなかった。でもやっぱり「習い方」なのである。この本では技術解説と同じくらい、剣道に接する心構えについて説く。如何なる態度、心がけで剣道を習うか、まさに「習い方」について説くのである。 戦後剣道の原点を写すものであり、そして「習い方」について綴られた本、それ故の価値があると思うのである。 又、歴史的な意味もある。剣道も他の競技と同様、規則がある。それは年々変っていく。規則が変る、という事は競技としての剣道の有り様が変る、という事でもある。その変遷をこの本で感じる事も出来るのである。専門的になるがいくつか例を挙げる。 組打 自身の竹刀が打ち落とされた場合等、相手に組みかかり、肉弾戦(おおげさかな)を行うというもの。これについての技術説明があるのである。今は勿論、存在しない。 足搦 相手の足に自分の足をかけその体勢を崩す技術。これも今は、おそらく反則扱いになる筈である。 撓(しない)競技 剣道がGHQにより禁止された際、に作られた競技。殆ど剣道と同じ。今はこれもない競技のはずである。 このように剣道の歴史で今はもう無いものも見出す事が出来るのである。正に歴史を「感じる」事が出来るのである。 特に今回この本を読んで改めて感じた事があった。それは言葉は受け手によっていかようにも変化するという事である。 一つ例を挙げよう。『懸待一致』という言葉が載っていた。 懸かる事と待つ事は同じであるという言葉である。この言葉、意味を理解はしていた。しかし使い方がいけなかった。待ちの肯定に使っていたのである。待ちも懸かる事と同意である、だから待っていいと。この言葉、本来の意は待ち、懸かりという二元化の否定にあると思うのである。相対する二つのものに分けたりしない事、「自然体」を表すものだと思うのである。 「自然体」剣道でもっとも大事にされるものである。だからこそこの言葉もこう捉えるほうがよりしっくりくると思うのである。それが今のこの言葉の私なりの受け取り方である。 本は世界に星の数ほどある。そこから何を得るか、それは半分は本の力、後の半分は自分自身の「何か」だと思うのである。そしてそれはその時の自身を映す鏡にもなりうる、されに言えば本の遍歴、本の読み取りの変化は、同時にその人の歴史に通じるものもあると思うのである。そう思ってのジャンル無しの書評である。 古い本との出合いもまた一興。みなさん古書店はどうでしょうか? |
|||
| 今日のあれこれ | |||
| 友と痛飲した。かなり親しい友でも意思疎通は難しいものだと感じた。 メール一通でも誤解が生じる(メールだからという面も多々あるが) ツールが発達すればするほど、コミュニケーションというものは難しくなっていくのかなあ、そんな事を感じた今日。 道具に使われず、道具を使う人間になりたいと思ってはいるのだが、中々…コミュニケーション自体にびびる自分、まだまだ精進である。 ふらり、ふらふら。ふら、ふらら。 |
|||
| 本日のお勧めリンク | |||
| 古書・古本のススメ http://www.kosho.or.jp/ (日本の古本屋 古本・古書検索サイト) http://www.ebookoff.co.jp/top.html (eブックオフ) |