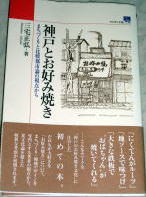| 2005年6月7日(火) | |||
| no.34 神戸とお好み焼き 三宅 正弘 著 | |||
|
|||
|
今日は少し地域性の強い本である。ここの所、関西の方の本が続いているが、これは本当にたまたま…というか、第二の故郷である大阪になつかしさを感じているからである。勿論今いる埼玉も大好きではあるが、それとは別である。埼玉(関東)と大阪(関西)の違い、私が感じるのはやはりラジオである。ラジオはテレビよりずっとローカル色が強い。その為、その地域のみの番組が今だ存在する。僕の場合は関東なら永六輔の土曜ワイド、関西ならおはようパーソナリティー道上洋三です、がこれぞというものである。今はWEBで聞けるようにもなりつつあるが、やはりこのラジオを当地で聞くと、「居るな〜」と感じるもんである。これは音で感じる「居るな〜」感である。
その地域に「居るな〜」と感じるもの、他に何があるだろうか?私は大阪の方は淀川沿いの下町が第二の故郷である。その為、銭湯の存在にも強く「居るな〜」と感じる。このようにある場にも「居るな〜」感を感じる事が私にはある。 さて紹介に入っていく。この本はその『場にある「居るな〜」感』に関する一冊であると言える。神戸と言う都市にあるお好み焼きやさん、神戸に「居るな〜」と感じさせるお好み焼きやさんに関する一冊なのである。 本はお好み焼きやさんについて考察をしていくのだが、その流れが秀逸である。まず、神戸のお好み焼きの特徴でもある、地ソースについての考察から入っていく。(地ソース≒中小メーカーが作り地元で消費されるソース) そして更にお好み焼きの特徴、混ぜ型(具と生地を混ぜる)とのせ型(生地をまず薄く鉄板に敷きそこに具を載せ更に生地をかけ、のせる)について、神戸でのお好み焼きのルーツ等から考察をする。 最後には、この焼き方の特徴から店の作りの特徴を考察し、現在の都市空間にはとって、どのようなお好み焼きやさんが必要か?という考察にまで至るのである。 惜しむらくは、本のボリュームである。非常に斬新な一冊なのだが、少しページが足りないと感じた。一つ一つの着眼点が非常に素晴らしいものだけにもっと詳しく読んでみたかった。しかし、考えようによってはそれもまたいいのかもしれない。このページ数により間違いなく「読みやすさ」は確保されている。それに加え、この本がスターターになる可能性もある。それにこのようなテーマで難しいのは資料の集め方であろう。それを考えてみればやはりこの本は読むのに十分に値する一冊であると言えよう。 本のボリュームが少し物足りない、しょうがないという所はあるが、しかし様々な発見がこの本からは得ることが出来る。地ソースの存在。神戸ではお好みの事を元々にくてんといった事。広島焼きスタイルはもともと関西にも存在したという事等等。先に資料の集め方は難しいと書いたが、これだけの事を書物と言う形で残した、ということにも意味があるような気がする。 最後に名前つながりで一つ思い出したこと。この本を読んで、神戸から大阪を思いつつ、思い出した味は「イカ焼き」であった。こちら関東で「イカ焼き」といっても「イカを焼いたやつ?」と聞かれどうも通じない。私も暫く食べていないがお好み焼きに近い感じのであったと思うのだが…。祖父、祖母と何度も食べた想い出がある。祖父亡き今、思い出の一品である。今度行った時には是非探してみたい。 久し振りに関西に行きたいな、そんな事を感じた本であった。関西の人も、そうでない人も読んでみては?新しい発見があること請け合いである。 |
|||
| 今日のあれこれ | |||
| 一つの道から 最近、ある道が気にかかる。遊びの道、剣道、柔道…ではなく、本当に町にある一本の道である。大学の近くにある一本の道である。かわいい子が通るから…ではない。気になるのである。その道は人通りが多くないのに飲み屋が多い、異様に多い。そのどれもが結構古い店である。なんでここにこんなにお店があるのか?翻ってなぜこの道に…そう思い、最近調べている。 調べていると、いろいろな所へ飛んでいく。その道の近くには旧村社がある。そこの成り立ちからアプローチしてもいる。そうすると神社合祀の事を勉強する事になる。更にそれに関連し、明治の町村合併のお勉強、そこから文書(もんじょ)の読み方へと飛んだり…。かと思ったら、その神社に疱瘡神様が祀られていて、なんで祀られているか考えるうちに、その地域の地形の特徴を考えたり、更にはその神社の碑文の拓本をとったり…。 道一本調べるのにいろんな学びが出来ていて…面白いものである。 最近あるサイトの管理人さんとメールのやりとりをしているが、その中で「知らない事」というキーワードが出た。私もその多さを痛感している。ではどう学んでいくか。私は今、たまたま一本の道から、どうしようもなく(笑)広がっている。これが自分は好きである。もう一つこれが好きなのはこれは「入れて・出して」が繰り返し出来るからである。養老氏は言う。人間の脳はこの繰り返しによってのみ学習が可能であると。本での学習は「入れて」は出来るのだが。一人での学習は「入れて」は出来るのだが。この「出す」という事。これは結構難しい事だと最近考えている。だから、道という外のものを歩いて(出して)また入れて…これが好きなのである。 この方とメールできるのも、この「出す」事の一環として非常に大事なものだと感じている。 こういう事は苦境に立たされれば、立たされるほど感じる事。己の無知を恐れ、出す事を恐れていては結局、学びは出来ない。それは脳の構造からも明らかである。個人で学んでいてもそれは学習足りえるか?非常に難しい事である。寧ろ周囲の刺激のある集団の学びの方がずっと初歩の学びであると思う。 出す事・入れる事。これは各自の自由。それをする場って実は結構貴重だったりする。そんな事も無くさないと、あるいはそこから考えないとわからない。 「出す事」それを考えないと学びは…そんな事をふと一つの道をみつつ感じた今日。 もちろんこのサイトも「出す」一つ。読んでくださっている皆さんには心から感謝しています。 ありがとうございます。 |
|||
| 本日のお勧めリンク | |||
| http://kitsutsuki.moo.jp/index.html (きつつきのHP 京都のコーナーがあるので…後は着物、漆器のコーナーも。以前、浴衣を作る注染の職人さんと、漆、を塗る、漆刷毛の職人さんのお仕事を見せていただいた事があります。漆刷毛の材料には人毛も使うんですよね。そんな事こんな事たくさん頭に浮かんできたので関西つながりでここを今日のオススメに。) |