| 2006年6月3日(土) | |||
| no.60 温泉教授の温泉ゼミナール 松田忠徳 著 | |||
|
|||
マガイモノの温泉
この題でくれば、当然出てくるのは「ホンモノの温泉」である。松田氏の本での一貫したテーマはこの「ホンモノの温泉」を提唱し、そして明らかにしていくことであると言える。その最初の一冊、「ホンモノの温泉」そしてそれが持つ「温泉力」について提唱したのがこの本である。 この本では「ホンモノの温泉」に相対する概念として「マガイモノの温泉」が取り上げられ、テーマとして扱われている。この本が出された当時、この「マガイモノの温泉」は人を殺してしまっていた。「温泉」で人が死ぬ、このような事件の中、今の温泉の実情をこの本は告発した。 温泉法には違反しないが、本来の温泉の性質を無視した「マガイモノの温泉」。その代表例として「循環風呂」を取り上げている。 「循環風呂」とはいかなるものであるか?下の図を見て欲しい。 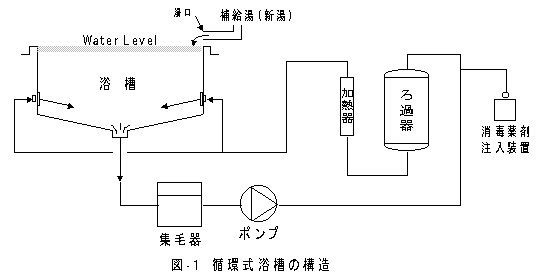 (厚生省 循環式浴槽におけるレジオネラ菌感染防止マニュアル より) これを見ていただけると分かると思うが、温泉を消毒・ろ過し繰り返し使いその後に、一定期間でお湯をすべて取り替えるシステム、これを「循環風呂」という。これに対し本書で指摘されている問題点を整理してみる。 まずは事件の際に原因となった事である。一つはお湯を取り替える頻度、事件になった浴場の場合は1週間に一度取り替えていたという。更に塩素がきちんと投入されておらず、更には新しいお湯を本来は少しずつ足していくのであるが、それも行われていなかった。これら循環風呂における人災、これらが問題となっている。 それに加え、筆者はここで使われる塩素を問題視している。具体的にいえば、塩素自体が細胞を破壊する効果を持っている事、塩素から生じるトリハロメタンを問題視しているのである。更にもう一つは塩素という科学物質の混入により様々成分により効能が生じている温泉の本来の性質が奪われてしまう事、これら3点を問題点として主張しているのである。 (これが正しいかの検証は本書では十分とは言いがたい) そして筆者はこれらの対策を次のように述べ、更には展開している。一つは温泉の遣われ方に関する情報を公開する事である。ここのお湯はどのような使われ方をしているか?「循環風呂なのか、それとも古くからの源泉かけ流しなのか?」それを提示し、その上で利用者に選択をさせるべきではと言っているのである。(つまり循環湯自体を否定はしていない。) 次が「展開をしている」と書いた由縁である。そしてこの筆者の功績ともいえる点である。それは「ホンモノの温泉」としてこれまで長い間培われてきた温泉のあり方を「温泉のあるべき像」として提示しているのである。具体的にいえば100%源泉かけ流しの形をである。そしてこの「ホンモノの温泉」が筆者の言う「マガイモノの温泉」のより今、危機を迎えている事を述べていくのである。(それは経営面等で)更に最後にはこの「ホンモノの温泉」により温泉本来の力を活かし使う事、これが温泉の究極の楽しみ方なのではと提唱するのである。 決して、正面きって循環風呂を批判していないが、それでいてやんわりと湯気のように「ホンモノの温泉」、それを楽しむ事を提唱し、そこに主張をこめているのである。 アマゾンの書評にもあったが、確かに「ホンモノの温泉」が何か?それは本書では根拠が十分であるとはいいがたい。更にそれが具体的に(科学的に)より良いものなのか?という面は本書では明らかになっていない。その点は課題であるが、「あるべき像」を提唱した事、それがこの本の第一の意義であると私は思う。 更にいえば、筆者もその点は気づいているのではないだろうか?その後の著作でこの点はだんだん明らかになってきていると思う。それを見極める意味でもこの本をはじめとして、是非何冊か味わってみて欲しい。 今日の温泉の姿を知る上での好著、是非ご一読を。 |
|||
| 今日のあれこれ | |||
温泉本です。今、温泉で卒論を書こうとしていますが、その時に立ちはだかる大家の一人、それがこの松田氏です。アマゾンで評されている通り、論理をつかった論文ではありません。しかし彼が今日の温泉に関する話題に大きな影響を与えた事は紛れも無い事実です。 その対極とも言える人に山村順次氏がいます。彼はそれこそ論理を使った論文で(特に地理学から)温泉を40年近く研究してきた方です。その多くの研究は温泉地の特徴、性質を明らかにしています。記録になっています。 しかし、今日の温泉の諸問題に対し、寄与した度合いを考える時、どうしても山村氏の研究は松田氏の著作に比べ、おちると言わざるを得ません。それはなぜか?一つは今日的課題から研究が乖離していた事、もう一つは温泉そのものについて山村氏が扱ってこなかった事ではないかと私は考えています。 勿論、それは学問のあり方であり否定はしません。そして松田氏の著作を全面的に肯定する訳でもありません。 しかし、学問が即時的に影響を与える、つまり「今ある問題の解決に何らかの役に立つ」可能性はまだまだあるんじゃないかと思っています。 松田氏のアプローチで山村氏のように研究する事、それも可能なのではと思うのです。 では、どのようにするか? (ここには大学の役割とは?という大きな問題も絡んでくると思うのですが) 悩みつつ、取り組み中です。 一つ。 温泉法が改正され松田氏の提唱した温泉の利用法の提示が義務図けられました。 やっぱり…この働きは見落とせないんだよなあ…。 |
|||
| 本日のお勧めリンク | |||
| http://www.env.go.jp/nature/onsen/kaisei_panph.pdf 改正温泉法の説明です(PDF)。 |
