| 2005年7月6日(水) | |||
| no.40 江戸のおトイレ 渡辺信一郎 著 | |||
|
|||
何処か遠くへ…行きたい…   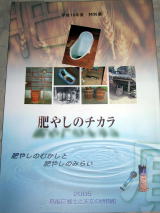  今日は久し振りに調査にでた。テーマは『肥やし(人糞)とトイレ』左2枚の図録とミュージアムグッズを求めて葛飾区へと行った。(ちなみに一番左のペーパー青いのは星に関するマメ知識です)最近江戸時代のリサイクル文化、中でも人糞について調べているのだが、その一環での調査が今日の目的だった。勿論ついでに帝釈天(右2枚)にも行っては来たのだが…。町で出会う人、もの…すべての出会いが一発勝負である。だからまち歩きは好きである。丁寧に接する事が出来るから。実生活で対人で丁寧に接すればその重さが嫌われる事が多い。特にコミュニケーションは。 そうでないまち歩き。だから私はまち歩きが好きである。 さて今回はその調査の一環で読んだ本の紹介である。題名ズバリ!の「江戸のおトイレ」である。この本は主に川柳、そして絵図をとおして江戸時代のトイレ(主に女性の)の実態、文化について書かれた一冊である。 この本の特徴、それはやはり主材料に川柳を用いた事であろう。この着目点が面白い。トイレ。近年「肥やし」についてはその研究が進んでいる。それは何故かと言えば資料が出てきたこと。個人宅の蔵などが開き、そこから「肥やし」に関する資料が出てきた為、その資料の存在ゆえに研究が進んでいるのである。 対してトイレである。その資料は…、と考えると中々容易には浮かばない。そうすると研究としては壁にあたる。どの資料に出てきてもらうか?そこで川柳に着目したこの本の価値が出てくると思うのである。 何か物事を考える際と同じで、こういう研究も「視野」がポイントになる、と私は思う。一つの事象について深めていく時、どういう「視野」で見ていくか?どれだけ多角的な「視野」でみていくか?そこにその研究の正確さ、論理性が含まれていると思うのである。 勿論物事を考える時もそれに近いものがあると思うのである。以前地図、そして実測図の例からその点に触れたことがある。(参照) 人間関係についても然り。自分がどんなに正しいと思っていても(自分はそれが多い)ちと視線を変えれば、それはとんでもない事だったりする。こういうのってとっても疲れる。正直めんどくさくなる。でもこの「視野」が一つに固まった時、それはある意味もっとも生きずらい世界になってしまうと思うのである。やっぱり「盗人にも三分の利」で…。 生きずらい世界つながりで本に戻す。今とトイレを比較した時に見えてくるものとして、その排泄物の行方についての事があるのではないか?過去のトイレはその流れが見える。出されて(勿論そこも見える(笑)その辺は本書参考)出された糞尿は肥として商品として回収され、町の中を通り、農産地へ行き、肥料として用いられる。そしてそこで作られた野菜はまた逆のルートを辿り、町に戻っていく。(糞尿の代金の換わりにその野菜を出すと言う事もあった)かつてはこのように流れが人の目に見えたのである。 翻って現代はどうであろう。あなたがトイレに入る。多くは水洗式であろう。水を流す。「ジャ〜」自分の排泄物は水とともにブラックホールに吸い寄せられたかのごとく吸い込まれ、もうそこで見えなくなってしまう。さてこの排泄物がどういう経路を辿っていくかあなたは説明できるだろうか? 何となく下水にいって、そこから処理場に行って、川に出て…。言葉は浮かぶ。ではその風景は?私は浮かばせる事が出来ない。(このあたりはこの本が詳しい) これって少し問題なんじゃないかな、と私は思っている。自分と対象の連続性が切れてしまっていると思うのである。他に言えば、食肉などもそうであろう。パックの肉と生きている牛・豚・鶏。この間がすっぽり抜けている。これって少し不自然なんじゃないかなあと思うのである。この不自然さがある意味いびつな社会を生み出しているのではないかと一人思っていたりなんかする。 政治…なんかもそうである。郵政民営化。近くに郵便局はあるのに、何故かニュースで聞くと「なんじゃあれ」。何か切れているのである。国会自体も何か遠い気がしたり…。 もちろんこれは社会の発展という事も出来よう。しかし、この見えなさ、連続性の断絶ってやっぱり何処かで「生きずらい世界」につながっているんじゃないかと思うのである。だからこそこの本のように江戸のトイレに着目し、考える事もその再生という面で意義があるのでは?と思うのである。 更に今回のおトイレの話題は精神的にも汚い所、としてその関係性を積極的に切る場所でもあると思う。穢れ・汚れという発想である。そういう意味でもトイレに着目した意義はあると思うのである。 そんなこんなでこの本である。こんなややこしい事は考えずに、中々取り上げられないことだけに新しい発見、知との出会いが豊富にある本書である。是非手に取ってみてほしい。 |
|||
| 今日のあれこれ | |||
| 戯言&私信です。どうぞ気になさらずに。 【約束】 自分の今回の出来事で一番のキーワードになる言葉である。それだけに怖くて取り上げられなかった言葉でもあるが…。 おおまかに言えば私は今回「公」で約束を破り続けた人に対して我慢ならなくなり、その情が「私」にまで及び、必要以上にその人を傷つけたと言う流れである。 今回の事があっても、変わらなかった考えの一つは、「公」で約束を破り続けた人に「信」は集まらない、という事である。 では、それは何故だろうか? またまた山田ズーニーさんの説を使ってみよう。 彼女はこう言った。 「昨日の私は今日の私ではない。昨日までやっていたことは、ぜんぜん今日の私に結びついていない。明日の私もぜんぜん違う。今日やっていることは何一つ、明日の私につながらない」 では、何時の貴方を信じたらいいの?これからどうなってしまうの?あなたはなんなの?となってしまう。 これはつながりの危機だ。 過去から現在そして未来へと、連面に続く時の中で、その人が何の脈絡も持たず、ブツッ、ブツッと途切れた感じがする。こういう状態だと不安になる。 信頼の条件…ポイントはつながりだ。 過去から現在そして未来へと続く時間の中で、あなたの連続性が感じられること。 人と社会のつながりが見える事。 ここで必要とされるのが約束であると、私は思うのである。人は表現を介し理解される。心で…という部分も勿論あるが、それは「信」あってこそ、である。その表現の一つの言葉、それが成立する事、それがつながりの危機を防ぐ一つの大きな手段であると思うのである。 これが公私共に1年近く守られない人と付き合ったらどうなるか? 一つ一つに約束を守れない理由があろう。しかし1年である。 それで癇癪を起こす。一年待ったとしても癇癪を起こす事が攻められるのだろうか? 周りの近しい人、その事をご存知でこちらに意見をされたのでしょうか? だから最後、癇癪をおこした時、彼女との関係よりも約束を守ってもらう事を望んだのである。 一度でも、「誠」が見たかったのである。 だからその先に「別れ」があったとしてもいとわなかったのである。 (その点は仲介してくれた人も含め、理解されることは無かったが) 大切な人だからこそ、約束の意味を少しでも知ってほしかった。というのは、あまりにもキレイ事か…。 ただ自分の思いに理があればこそ、その伝え方には慎重にならなければいけない、という事も今回知った。 それを知らず、自身の未熟さで周りに迷惑をかけたこと、これも反省である。 でも、これは声を大にしていいたい。個人でも集団でもある「型」を持ってこそ、信であったり、協調は生まれるのだと。一人一人の独自性を認めることは、好き勝手やることではない。ある型を守ってこそ集団の中で独自性が発揮される。 「守破離」剣道の言葉で剣の習得段階を表した言葉であるが、守なくして破、離はないのである。今周囲の問題のキーはそのへんにあると私は確信している。 |
|||
| 本日のお勧めリンク | |||
| http://www.city.katsushika.tokyo.jp/museum/(葛飾区郷土と天文の博物館 かつて「肥やしのチカラ」という特別展が行われました。図録はまだ販売中) http://www.oikura.co.jp/ecoreport/eco017.shtml(おいくらエコロジーレポート リサイクルの歴史(1)) http://eco.goo.ne.jp/business/csr/lesson/dec00.html(環境GOO WEB講義「植物国家としての江戸」) |
