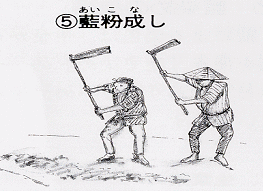ここでは藍染めに用いる、藍についてその種類と、栽培方法についてみていきたいと思います。藍の色素を持つ植物は植物学上の分類では13種類存在します。それらを用いて、世界中で藍染めが行われていますが、その中で日本に産するものは「琉球藍」「蝦夷大青」「染物蔓」「蓼藍」の4種類です。ここではそれら13種類の植物から代表的なものを取り上げ、紹介をしてきたいと思います。また栽培法については日本国内で主に栽培されていた「蓼藍」を取り上げていきます。
今回は藍分を持つ植物でわが国の中で代表的な5つを紹介していきます。一つ目は川越を含め関東地方で主に栽培された蓼藍についての紹介。そして二つ目と三つ目は日本の鹿児島、沖縄などで使われた、琉球藍、アイヌの人が使っていたタイセイ。その次、4つ目はヨーロッパで使われたウォード。そして最後は、五つ目は主に古代インドで使われ、また明治期、日本で主に栽培されていた蓼藍より藍分の含有率が多いため、輸入され、使用されたインド藍。
藍と一言にいっても、その実態は様々。それを藍分を持つ植物の多様性の面から感じていただければと思います。